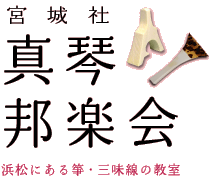「つぶやき」カテゴリの記事一覧
■ 和洋奏楽 本番に向けて
2011年10月23日
10月30日の「和洋奏楽~生涯学習フェスティバル」まで一週間となりました。
本番に向けての練習だけでなく、前日のリハーサルから当日の運営、タイムスケジュールと分担表作り、箏の調絃の段取り、担当者決め、プログラム構成、舞台の進行台本、ゲストとの打ち合わせ、チケット販売等々・・・毎日やることが山のようにあって、崖っぷちのスリルを味わっています。睡眠時間も最小限に・・・
今日は、浜松ジュニア・ユース邦楽合奏団の最後の練習でした。子どもたちは初舞台をとても楽しみにしていて、今日は最後の仕上げ!をみんな頑張りました。結成して半年ですから、技術的にはまだまだですが、気持ちのこもった演奏を聴いていただけると思います。是非応援お願いいたします。
明日は春の海の練習です。人間国宝の山本邦山先生と春の海を共演させていただけることは、本当に光栄です。新たな気持ちで、春の海の一音一音を大事に演奏したいと思います。
自由席チケット、学生券はまだ十分にありますので、ぜひ聴きにいらしてください。きっとご家族で楽しんでいただけると思います。
当日券もあります。
お待ちしています。(理)
■ 中秋の名月を愛でる会inオークラ・アクトシティ浜松展望回廊
2011年9月13日
今夜はお月見 ・・・今、ちょうど真上にまんまるお月様がきれいに見えます。日本の秋ですね。朝晩はめっきり涼しくなりました。
・・・今、ちょうど真上にまんまるお月様がきれいに見えます。日本の秋ですね。朝晩はめっきり涼しくなりました。
昨夜、一足先に中秋の名月を愛でる会がありました。オークラ・アクトシティ浜松45階から、本当に美しい名月 を愛でながら、リコーダーカルテットの素敵な演奏を聴き、おいしいお料理を堪能し、いろいろな方々と楽しいおしゃべり・・・とっても贅沢な時間を過ごしました。
を愛でながら、リコーダーカルテットの素敵な演奏を聴き、おいしいお料理を堪能し、いろいろな方々と楽しいおしゃべり・・・とっても贅沢な時間を過ごしました。
月は一年中出ているし、満月は28日周期で見ることができますが、「月」といえばやっぱり「秋」です。月夜の晩、と言えば秋の夜。虫の声を聴きながら、美しいお月様を見ていると、何とも言えず幸せを感じます。季節の移り変わりを五感で感じとることができる日本人に生まれてよかったと、感謝感謝!
残暑ももう少しでしょう。秋は栗、秋刀魚・・・美味しいものがいっぱい。実りの秋、そしてやっぱり「音楽の秋」です。10月30日のコンサートに向けて、練習だけでなく、いろいろな準備を進めています。お楽しみに! (理)
■ 志の輔&志の春inアクトシティ浜松
2011年9月4日
気ままな台風の進路を心配しながら、アクトシティ浜松(しかも何と大ホール)で立川志の輔さんの落語を聞きました。志の輔さんの落語は(私なんかが言うのはおこがましいことですが)とにかく「いい」「おもしろい」「楽しい」。落語そのものももちろんですが、枕の話がまた最高!!誕生したばかりの野田内閣のこと、台風のこと、ひいては気象予報士のこと・・・どれも「そうそう!その通り!私もそれを言いたかった」みたいなことをタイムリーに語ってくれて、思わず笑って引き込まれ・・いつの間にか落語の演目にそのまま持っていかれ・・気がついたら(一つの演目で)1時間半近く経ってました。
でも、全然長いと感じないのです。すごいです。滅多にやらない演目(現在では志の輔さんだけらしいです)を今回聞かせてもらいました。正に話芸、日本の伝統文化です。座布団と手ぬぐいと扇子だけで1500人以上の人たちの心を3時間掴んじゃうわけですから。
その偉大な志の輔師匠の三番弟子の志の春さん!偉大な師匠を選んだ目は確かだったようですね。一層精進して、アクトシティ中ホール(大ホールとは言いません)で聞かせてもらう日を楽しみにしています。 (理)
■ あおによし 奈良の都・・・
2011年8月18日
この夏休み、一番楽しみにしていた奈良旅行に行って来ました。
連日の猛暑の中!です。この一番暑いときに!です。昨年の平城遷都1300年祭がウソのようにどこも人が少なくて、ゆっくり見ることができました。熱中症にならにように梅干しをバッグに忍ばせ、ひんやりタオルを首にまき、アームカバーに日傘、暑さ&日焼け対策は完璧!
薬師寺、新薬師寺、興福寺、平城京資料館、平城京内裏、元興寺と回り、充実し過ぎた二日間でしたが、なんと言っても、歴史・文化遺産研究家の山下孝先生の解説が素晴らしく、目からうろこ!私は日本の歴史遺産、文化について何もわかっていなかった!ということがよくわかりました。
薬師寺の東塔(これから修復に入ります)、興福寺の阿修羅像・・・その他とてもここでご紹介できませんが、奈良には数多くの国宝があり、都の変遷の跡が残り、日本人のルーツがそこにあります。とにかく現地に行って、自分の目で見て、肌で感じることです。
最後に寄った大乗院の庭園は、それはそれは品よく、美しく、水面に写る景色が風に揺れる様は本当に素晴らしく、暑さを忘れました。一日中そこにいたい!!と思いました。全て考えて作られた庭でありながら、自然の美しさと自然の中にいる幸せ感が心に沁みました。
やっぱり日本人の感性は素晴らしい!そして、奈良時代の建築技術は今より上だったのではないか!と、日本人であることを誇らしく思いました。
文化はなんとしても受け継いでいかなくてはならないと思います。日本文化を継承できるのは日本人だけですから。(理)
■ 音の歳時記
2011年8月17日
 皆様,残暑お見舞い申し上げます。暑い毎日ですが、暑気払いに面白い本をご紹介します。。釣谷真弓著の「音の歳時記」~四季折々の日本音楽~、です。箏の演奏家であり、また世界各国を旅しては、その国の民族楽器の歴史や文化を研究したりしている方ですが、日本音楽の奥深さを、肩の凝らない切り口で紹介してくださっています。たとえば、夏の音と題して、「田んぼの音楽・・・・カエルの合唱、祭りの音とリズム・・・・笛・鉦・太鼓、森のシャワー・・・・ニイニイゼミとアブラゼミ」といった具合です。改めて、日本人は、森羅万象、四季折々の暮らしの中に音楽を感じて生きてきたと、実感させらせます。ちなみに、宮城道雄先生は、蚊のぶ~んと飛ぶ音に、篳篥(ひちりき)の音を感じていらしたようです。東京堂出版より出ています。貴重な写真も数多く掲載されており、とても丁寧なつくりで、きっと楽しんでいただけると思います。8月、葉月も後半になれば、秋はもうすぐ・・・・・・演奏会のシーズンも間近です。 Mi-chi
皆様,残暑お見舞い申し上げます。暑い毎日ですが、暑気払いに面白い本をご紹介します。。釣谷真弓著の「音の歳時記」~四季折々の日本音楽~、です。箏の演奏家であり、また世界各国を旅しては、その国の民族楽器の歴史や文化を研究したりしている方ですが、日本音楽の奥深さを、肩の凝らない切り口で紹介してくださっています。たとえば、夏の音と題して、「田んぼの音楽・・・・カエルの合唱、祭りの音とリズム・・・・笛・鉦・太鼓、森のシャワー・・・・ニイニイゼミとアブラゼミ」といった具合です。改めて、日本人は、森羅万象、四季折々の暮らしの中に音楽を感じて生きてきたと、実感させらせます。ちなみに、宮城道雄先生は、蚊のぶ~んと飛ぶ音に、篳篥(ひちりき)の音を感じていらしたようです。東京堂出版より出ています。貴重な写真も数多く掲載されており、とても丁寧なつくりで、きっと楽しんでいただけると思います。8月、葉月も後半になれば、秋はもうすぐ・・・・・・演奏会のシーズンも間近です。 Mi-chi